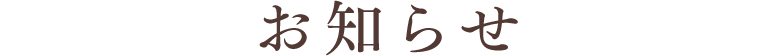2025/03/17その他
生産地インタビュー 黒糖工場はゴミを出さないとってもエコな工場
<生産者との取組み>沖縄県黒糖② JAおきなわ小浜島製糖工場
第一回目リポートはこちら 小浜島 北村ご夫妻インタビューhttps://www.eitaro.com/news/other/20250313/2756/
当社の榮太樓飴「黒飴」などに使用している沖縄県の黒糖。小浜島と西表島の黒糖をブレンドして使用しており、小浜島黒糖は戦前より使い続けている長い歴史があります。
.jpg)
▲当社が使用する黒糖生産地の小浜島と西表島は日本の最西端にある島々です。
初日に訪れたのはJAおきなわ小浜製糖工場。小浜島は面積7.86㎢、人口は748名493世帯の島。「ちゅらさん」でおなじみ、シュガーロードや海岸線の美しさが人気です。小浜製糖工場に勤務する北村晃子さんにお話を聞きました。
今年の生育状況は雨も適量で日照時間も多くあったため収穫量としては前年以上に良いそうです。台風の直撃はなかったものの、10月下旬に接近した台風の影響で、風で引き裂かれた葉を再生して育てようとして糖分が全体に行き渡らず、最終的に糖度は低い傾向にあるようでした。昨年、一昨年と台風が少ない年は秋ごろより葉の裏に群がるようにアブラムシが大量発生します。葉に吸汁するためサトウキビの成長を遅らせ、放っておくと病気を発症し光合成を阻害してしまうので駆除も大変な作業の一つです。小浜製糖工場の操業期間は1月~3月、サトウキビがいちばん糖度を蓄える時期であり、この時期は季節工を含め総勢70名ほど。毎日50tのサトウキビが運び込まれ24時間体制で黒糖を生産されています。サトウキビの収穫は二つあり、「手刈り」と「機械刈り(農業機械の総称名でハーベスタと呼ばれている)」で割合は手刈りが4割、機械が6割です。
すべてを機械化にしない理由は二つありました。一つは選別機械のキャパシティが追い付かない事、もう一つは雨が降り畑がぬかるむと機械が入れず作業が止まってしまうこと。収穫期に止めるわけにはいかないため、手刈り作業は必須だといいます。機械化が進む昨今ですが、全てを機械化できない事情があるのだとわかりました。ここからは小浜製糖工場内の写真とともにお届けします。
.jpg)
▲石垣島より小浜島へ向かう八重山フェリー。石垣島から30分ほどの距離です。
.jpg)
▲農家さんから毎日持ち込まれる大量のサトウキビ
.jpg)
▲左側が手刈りのサトウキビ、右側が機械刈り。機械で刈ったものは葉や梢頭部が残ったまま
.jpg)
▲機械刈りのサトウキビは葉や梢頭部を取り除くため一旦選別機械へ持ち込まれ、目視作業で選別されます。生きたハブも一緒にベルトコンベヤーで流れてくるとか
.jpg)
▲細かく裁断、選別されたサトウキビは機械で圧搾され汁を搾り出します。その際に搾ったサトウキビのかすは「バガス」と呼ばれ、ボイラーの燃料として活用されています。
黒糖の製造現場を見ながら感じたことは、黒糖工場はとってもエコであるということ。梢頭部は燃やして土に還したり、マンゴー農家の苗木の下に敷き草として使い雑草対策に役立てたり、牛の餌などに使われています。搾ったサトウキビのかすはボイラー燃料として活用されるなどSDGsという言葉が生まれる以前から、サトウキビの原料は余すところなく有効活用されてきたことがわかりました。実際に自分の目で現場を見聞きして、とても有意義な内容でした。
広報部